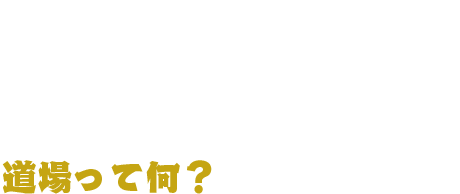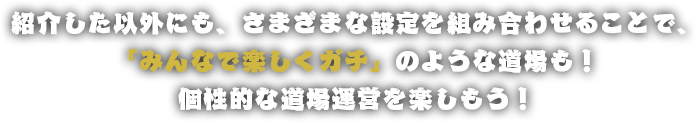あてどなく街を歩くF.A.N.Gに、少女が声をかける。
貧しいなりをした少女の瞳にF.A.N.Gは過去を思い出す......
蠱毒(中)
女の声がした。
男は足を止める。街灯の陰になった細い脇道の入り口に、女が立っていた。殺し屋と並ぶ、人類最古の職業。世界のどこにもある光景。この国の法では全面的に禁じられているにも関わらず、春をひさぐ女の姿は、そう珍しいものでもない。だが彼女は、女と呼ぶには若すぎた。
少女は上目遣いに男を見つめていた。貧しい身なりをしている。痩せた肩に、はかなさがあった。化粧気のない頬に、慣れのない愛想笑いが浮かんだ。
「おにいさん、お金ある?」
マッサージだと、決まり文句を口にする。黒い大きな瞳を、男は黙って見返した。
誘いに乗ったのは、多分に男の気まぐれだった。毒手の男が身に帯びた毒は、その精にすら及んでいる。男にその種の欲望はなかった。
ただ、微かなひっかかりがあった。まっすぐに見つめてくる黒い瞳が、男の何かを捉えていた。見たことのある目だった。男が忘れてしまった誰かの目だった。
「......こっちよ」
少女が手招きして、先に立って進む。現代的なビル群から景色が一変していた。急激すぎる経済成長が生んだ歪み。地方から経済都市へと流入し、仕事にあぶれて行き場をなくした貧しい人々の暮らす区画。無機的で人工的なハイテク看板の光が届かない、都市の暗がりだった。
廃ビルを思わす建物に、少女は男を招き入れる。あり合わせの布で適当に区切られたフロアの一角が、彼女の仕事場のようだった。薄暗い照明の下で、安っぽいベッドのシーツが、死んだ魚の腹のように白い。
くすっ。
部屋に入ったきり、動かないでいる男に、少女が笑いかける。
「一晩中そうやって突っ立っているつもり?」
侘しく寒々しい部屋に、ささやきは甘く響いた。それは、客の求めを熟知した老獪な女の声だった。自分の年齢に特別な価値があると知っている幼い声だった。何もかも理解して演じる女優で、正真正銘の
男は思い出す。少女の瞳に男が見いだしたもの。甘い声の響きの裏にあるもの。それが何だったのかを。
はかなげな少女の美しさは、強さを秘めていた。
その強さは、毒の持つ強靭さだった。
少女の黒い瞳。あれは、かつての自分たちの目だった。
毒手となるべく共に修行した、きょうだいたちの目だった。
......男は、ある一族に育てられた。伝説的な巫術師の一派にあって、
体術。武器の扱い。あらゆる毒の知識。古き暗殺の技はもちろん、機械や情報工学まで。暗殺者であるための、実践的な技能を徹底的に叩き込まれた。何より重要視されたのが、毒物への耐性だった。
毒に耐えるのは、毒のように暗くしぶとい生命の強さだった。毒を食っても生き抜くという執念だった。限界を超えた修練を耐え抜くには、毒のごとき強靭な意思が必要だった。
子供らの多くが脱落し、命を落とした。長い修行を終えたのは、男と、他三人の子供だけだった。地獄を共に生き抜いた四人には、血よりも濃い絆が生まれた。四人はきょうだいだった。毒使いとして選び抜かれた四人は、一族のエリートだった。きょうだいたちは、男の誇りだった。
「......おにいさん」
少女がいって、男は現実に引き戻される。
まっすぐに男の目を見ながら、少女は服を脱ぐ。透き通る肌が、侘しい明かりの下に浮かび上がった。男は身動き一つしない。
抱擁を求めるように両腕を拡げて、少女が男に近づく。一歩、また一歩。
その時、部屋を仕切った布の間に、人影が動いた。
「はい、そこまで」
姿を現したのは、少年だった。手にしたスマートフォンを、男に向けて構えている。
「悪いな、
少女の兄ほどの年齢か、少年はいっぱしの悪ぶった笑いを浮かべる。
「知ってると思うけど、こういうのは違法だぜ」
その上、相手が子供なのは外聞が良くないだろう。少年はスマートフォンをひらひらと振って見せる。
「SNSに流してもいいし......、当局に証拠として提出してもいいんだけど......。おじさん、どうする?」
美人局。仕掛けは悪くないが、脅す相手を間違えていた。どのデータベースに照会されても、男の身元が割れることはない。男は公式には、どこにも存在しない人間だった。
「く......」
男は小さく笑う。拙い犯罪者を始末するのは、簡単なことだった。男の毒が、二つの小さな身体を文字通り骨まで消すのに、数分あればいい。だが、男はそうしなかった。無謀な脅しを試みる相手に、またも気まぐれを起こした。
空気が変わった。男の手が、いつの間にかポケットの外に出ていた。魔法で取り出したかのように、札の束と短剣とが、それぞれの手にあった。
無造作に、男はその二つを床に投げる。床に短剣が突き立って、鋭い金属音が長く余韻を引いた。気をのまれたような少年に、男は低く告げる。
「......選べ」

























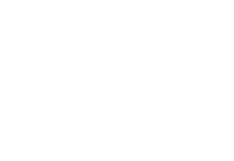 PlayStation および
PlayStation および