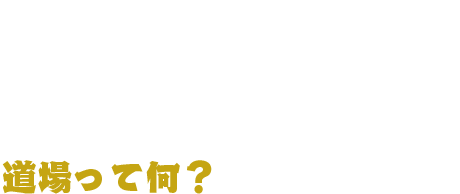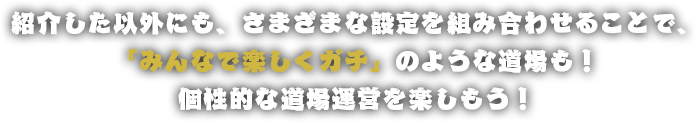「カレーでもごちそうしてくれ」
冗談のようにそういっていた賢人、
オロが、ある夜ダルシムを訪れる。
ダルシムの妻の手料理でもてなされたその後、オロは静かに問う。
「力とは何か」
賢人夜話(前)
夕餉の後、チャイのお代わりに首を振った客人を、主はポーチへと誘った。空気にはまだ少し、昼間の熱気の名残がある。風の通るポーチは、夜のひとときを過ごすのにちょうど良い場所だった。
「いやあ、旨かった。やっぱり本場のカレーは最高じゃな。インド人もびっくりじゃ」
客人がひょうひょうという。まばらな頭髪を風になびかせ、ぼろとしか言いようのない布ただ一枚を身につけた老人。
名を、オロといった。
仙人である。
ふふ、と主が笑う。ヒンドゥーの僧侶然とした姿。ダルシムという。
「ご満足いただけたようで、何よりです」
カレーではなく、マスール・ダールだとはいわない。サリーの作る豆の煮込みはこの州で一番だが、老仙人がカレーと呼ぶならカレーで構わない。
そんなことより。
ダルシムは静かに、オロと正面で向き合う。齢百と四十を数える、道を究めた仙人が、ただ夕食をたかるために、修行僧の自分を訪ねたのではあるまい。そのことがダルシムにはわかっている。
だが、そうなのかとは聞かない。ただ待った。
「ふむ......」
少しの沈黙の後、夜に向かって話すように、オロが切り出す。
「ぬしは、どう思う? サイコパワーとやらについて」
予想外の言葉ではなかった。
かつて、世界を覆わんとする強大な悪の組織があった。
シャドルー。
その首魁たる男が欲し、求め、身につけた悪しき力。その気配が今また現れつつあることを、ダルシムも感じていた。
その力を目のあたりにし、受け止め、闘った身として、ダルシムは応える。
「人が手にするには、危険すぎる力、と」
にょほっ。仙人が笑う。
「おもしろくない答えじゃな」
まじめすぎて、つまらん。そういって、オロは続ける。
「ならば、もうひとつきくが、ヨーガの力はどうじゃね? あれは、人にとって危険のない大道芸か何かか?」
ダルシムはむっとしかける。己が命も惜しまず研鑽を積んでいる
「いえ、老仙。ヨーガの力も、使い方を誤れば危険なことに違いはありません」
「ま、そうじゃな」
ダルシムをからかえなくて残念というようにオロは肩をすくめる。
それから、おもむろに、固めた拳を体の前に突き出した。
何気ないその動作が、すうと夜の空気を動かすのをダルシムは感じる。
とても、老人のものと思えない質量を備えた拳。千回のその千倍もの突きで、まさに打ち出した巌のようなフォルム。余計な力みなく、自然に握り込まれたその手が、見る間に青白く燐光を放つ。"気"の力。鍛錬と修養。ひたすらに強くあらんと高みを目指す格闘家がやがて至る、肉体を超えた力。次第に明るさを増す老仙人の闘気に、ダルシムは目を細める。
ぱ。
瞬間、老仙人は拳を開く。正拳を突き出す動作には移らない。もとより、闘うモードにはなっていない。今は。
拳に集まっていた青白い光は、蛍火のように、夜の暗がりに四散した。
「今のは、おなじみ"気"の力。このぐらいは、ほんの小僧ッ子でも使ったりしよるなあ」
「そう、ですね」
ダルシムは応じる。
気の使い手には、幾人も思い当たった。老仙人から見れば小僧かもしれないが、いずれも修練を積んだ
「では、次に......」
これはどうじゃ。
すうと、オロの目が半眼となる。
腰を低くおとして、構える。
細く長い呼吸をひとつ。
ふたつ。
「......!」
空気が、変わった。
我知らず、ダルシムは防御の構えを取っている。
いや、取らされている。
ぬるり。
空気が動く。
夜を闇ごと引きずるような気配に撫でられて、ダルシムの肌が粟立つ。
こおおおお。
オロの呼吸はいまや、地鳴りのごとく空間を震わせ。
常より表情の読めない双眸は、肉食獣のそれのように、紅い。
そうして。
揺るぎなく構えた拳に纏う。
夜よりもなお冥い。
闇。
(殺意の......波動っ!!)
即座に、ダルシムは覚悟を決める。
先ほどまで語らっていた仙人とダルシムとは、一撃の間合いにある。体半分、いや数ミリ退いた瞬間に、死が叩き込まれるのは確か。ならば。
ぱん。
ヨーガの道を究めし僧の両掌が、顔の前で合わせられる。
アグニの神へ祈るにも似た、格闘家ダルシムの
千回の、その千倍もの一撃を、この構えから放ってきた。
死を纏った仙人の突きを、受けるも避けるもない。
身を賭して。
磨き抜いた一撃で。
(滅する......!)

























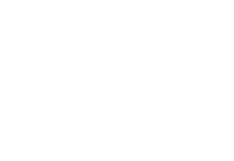 PlayStation および
PlayStation および