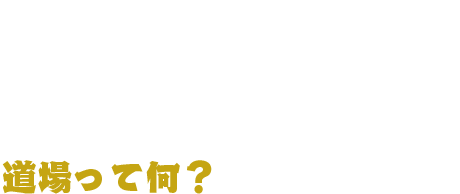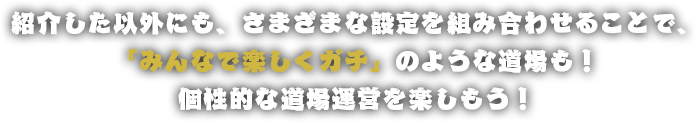ホリデイシーズンを過ごすため、一人息子のメルを連れて郊外の別荘に滞在するケンとイライザ。
降り始めた雪が静かに積もる夜、警備をくぐり抜けた何者かが家屋に侵入してきた......
冬の顔(前)
イライザが戸口に立って呼びかける。
「今日はおしまい。もう寝る時間よ、メル」
夕食の後、いよいよ雪が本格的に降り出したのをみて、四歳のメルは父親の手を引いて外に連れ出した。ベッドに入るまでの間だけと約束して、ポーチの端に積もった雪で遊びはじめる。そうして父親と二人、小さな
「ほら、びしょ濡れじゃない」
しぶしぶといった様子で部屋に戻ったメルを、イライザはタオルですっぽり包む。濡れた子犬みたいに震えながら、小さな息子は口をとがらせた。
「もう、ママ。もっとぼく、シュギョーしたかったのに」
「はいはい。修行はまた明日ね」
苦笑しながら、イライザは小さな格闘家の髪を拭いてやる。
「ははは、そうだなメル」
肩の雪を払って、ケンも部屋に入ってくる。身をかがめてメルと目を合わせると、拳を握って親指を立てた。
「今日の修行はばっちりだったぞ、メル。明日はもっとでかい雪だるまをやっつけような」
メルはぱっと顔を輝かせる。
「ショーユーケンで?」
「そう、昇龍拳だ!」
伸び上がったメルを、天に昇る龍のようにケンは高く持ち上げる。それから、ひょいと自分の肩に座らせた。
「でもメル、今日はもうベッドに行こうな。食べて寝て大きくなるのも修行だからな」
「わかった」
こくりと頷いたメルの頭を、ケンの大きな手が撫でる。イライザは息子の柔らかな頬にキスをする。
「おやすみ、メル」
それからケンは妻に少し目を向けて、踵を返す。肩に乗せた息子と何ごとか話をしながら部屋を出る。寝室のある二階へと階段を上がる足音が遠ざかった。二人を見送ったイライザは微笑んで、ほうと満たされた息をもらす。
窓の外では暗い空から雪がひっきりなしに落ちてくる。見渡す限り続く敷地は、どこまでも真っ白だった。この様子だと、明日はケンのいうとおり、大きな雪だるまが作れそうだとイライザは思う。
イライザは窓辺を離れる。ホリデイの飾り付けが済んだ広いリビングを横切って、暖炉のそばに足を運ぶ。よく乾いた薪をひとつ手にとって、火にくべる。そうして火に当たりながら、暖炉の上に並べたきらびやかなオーナメントを眺めていたら、ふいに後ろから抱きすくめられた。
「あっ」
ケンだった。力強い腕が腰に回されて、分厚く堅い胸が背中を押すのを、イライザは感じる。少しの間、目を閉じて感触を味わったあと、口を開いた。
「......わんぱく坊やは、もう眠ったの?」
首をくいと反らせて、イライザは背後のケンの顔を見上げる。
「ああ。メル坊ちゃんは、修行疲れでお休みさ」
ケンが答えて目を細める。くすり、とイライザは笑う。
「なんだ、何か可笑しいか?」
イライザはケンの腕の中で体を回して、正面で向き直る。それからもう一度笑って答える。
「メルと遊んでる時のあなた、すっかりパパの顔だったな、って」
ああ、とケンも笑う。道を究めんとする武道家。全米格闘チャンピオン。マスターズ財団の
「家族のためにパパをやるってのも、悪くはないさ。今年のパーティは家族を喜ばせようと、コスチュームも用意してあるんだぜ」
いたずらっぽくケンがいう。イライザは腕を伸ばしてケンの首に回した。
「あら、そのコスチューム......、セクシーな戦闘服だったりするのかしら、
答える代わりに、ケンはしなやかな腰を抱いた腕に力を入れる。イライザは間近から夫の顔を見上げる。まっすぐに見つめるケンの瞳に、暖炉の炎がひらめいている。この炎だとイライザは思う。この炎が私を夢中にさせたんだわ。
情熱的で、派手好き、エネルギーの固まりみたいな、炎みたいな男。その男のいちばん熱い炎は瞳の奥に、心臓の奥にある。肌が触れあうほどに近づいても、誰もその炎のすべてを知ることはできない。
ぱちり。
暖炉で火が爆ぜる。
イライザは強くケンにしがみつく。半ば開いた唇から吐息が漏れる。目を閉じ、ケンの炎にその身を投げ出そうとしたとき、物音がした。
「......?」
そっと、イライザの体がケンから離される。
一足早く気付いて、ケンは鋭い目を天井に向けている。音は、階上からだった。微かだけれど、確かに、何者かが移動するような音。メルが起きたのかしら。そういいかけたイライザの唇に、ケンは指を一本押し当てる。その顔に、先ほどまでの甘い笑みはない。
「上の様子をみてくる。何かあったらすぐに
有無を言わせない口調だった。ケンが脅威をかぎ取ったことが伝わって、イライザは体を固くする。パニックになりそうなのをおさえて、どうにかうなずく。
「よし」
小さくいって、ケンは走り出す。毛足の長い絨毯の上を、音もなく遠ざかるその背中を追うイライザの目に、涙がにじんだ。メルを助けて。そう叫びそうになるのをこらえた。いわなくても、ケンがきっとそうしてくれる。
足音を殺して階段を駆け上がりながら、ケンは考える。財団には、確かに敵は少なくない。契約書の外側でことを有利に運ぼうと、脅しをかけにやってくる連中がいても不思議はなかった。それとも......
ケンの脳裏に、ひとつの組織が浮かぶ。シャドルー。強大ながら邪悪な格闘家として、武を歪める者としてケンの前に立ったその総統、ベガ。またしても暗躍をはじめた奴らの手が、ここに伸びたのだとしたら。
ぎり。
ケンは奥歯をかみしめる。家族に手は出させない。
群れを護る獣の獰猛さが、ケンの顔に浮かんだ。

























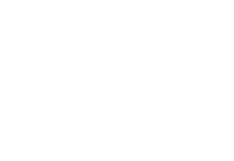 PlayStation および
PlayStation および