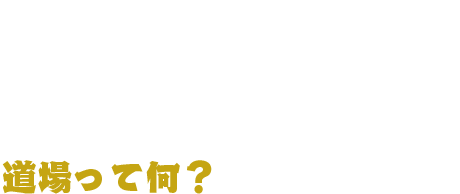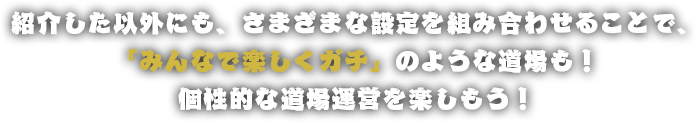そのさなか、オロの様子が豹変する。
老仙人は、突如として"殺意の波動"をまとって、ダルシムと対峙した。
賢人夜話(後)
その決意が、ダルシムの意識を、感覚を尖らせる。
身じろぎすらできない必殺の間合いで、オロの純粋な殺意がダルシムに迫る。
わずかな動きが、生死を分ける。
ダルシムは全神経を研ぎ澄ます。
己が肉体を世界から切り離し。
同時に己を世界に拡げる。
静かだった。
風がやんでいる。
ダルシムの頬を、汗がゆっくりと伝う。
時間が。
止ま。
る。
ぱ。
老仙人が、あっけなく拳を開く。
途端に、極限まで凝縮していた暗黒の波動は、跡形もなく霧散した。
にょほっ。
何事もなかったかのように、仙人が笑う。
「今のが、殺意の波動。ま、マネごとじゃがね」
ふう、とダルシムは息をつく。額の汗をぬぐう。
「驚かさないでください、老仙」
本当に
もちろん嘘だ。老仙人は、拳を解くその一瞬前まで本気だった。ダルシムの覚悟がまた、本気であったように。
くるりと体を回して、オロはポーチの柱に寄りかかる。
「サイコパワー、闘気、ヨーガの力、それに殺意の波動」
ソウルパワーなどというのもあるようじゃな。オロはあごに手をやって目を閉じる。
「わしが思うに、そういった力は、根っこのところでみんな同じなんじゃ」
指を一本立てて、老仙人は続ける。
「完全に同じ、というわけではない。じゃが、つながっている。同じだが、違う」
「同じで、違う......?」
「たとえば、そうじゃな。水面があろう、水のおもて」
オロは手のひらを一振りして、水の面を示してみせる。
「水の中にいる魚と、水の上を飛ぶ鳥。その両者からみて、水面は同じじゃろうか?」
同じ、ともいえるし、違うともいえる。ゼンの公案のようだとダルシムは思う。
「そう、ある意味では同じ。ある意味では違う」
オロが、ダルシムの考えを読んだように解説する。
水面は境界で、厚みを持たない。魚にとっても、鳥にとっても、水面は位置として同じだ。そして、水面の下には水が、上には空気がある。水面を境にして、それぞれ違う。
「境界というのがポイントじゃな。水面を越えて、魚はひとときであれば、空を飛ぶこともできよう」
「境界を、越える......」
老仙人は目を細めてうなずく。
「水面であれば上と下の二つの境じゃが...... "この世界"と別の世界の境界は、二次元の面ではありえない。それは恐らく、カラビ・ヤウ多様体のごときものじゃろう」
「カラ、ビ?」
ダルシムは返答に詰まる。この老人のいうことは、時々わけがわからない。
「ま、ともかく。この世界から別の世界への境界の越えかたが、ひとつではない、ということじゃ」
ふうむ。ダルシムは長い腕を組む。
「つまり、闘気の技も、サイコパワーも、私の
ぱちん。
オロが指を鳴らす。どうしてだか、変に若々しい所作が、老仙人には似合った。
「そういうことじゃな。さしずめ、修行して空を飛べるようになった魚、ってところかのう」
おぬしの場合、本当に飛ぶしな。そういって笑う。
ダルシムは考える。自分の場合は、アグニ神への信仰と、修行。それが境界を超えて、ヨーガの力として実った。そういうことだろう。
同じように、優れた格闘家たちは、心身の鍛練で境界を超え、闘気を身につける。サイコパワーや、殺意の波動にも、それぞれ越えるべき境界があり、手段がある。そんなふうに考えることができた。
「そして、その根源となる力、それは何か。じゃが......」
老仙人は自分の足下を指さす。
「たとえば、この
ああ。
ダルシムには得心するところがある。
ヨーガの修行。瞑想は、小さな己を、大きな宇宙へとつなげる。オロのいわんとしていることが、だから、修行を重ねた身にすとんと落ちる。
「なんとなく、わかりかけてきました......」
老仙人は目を閉じて、静かにいう。
「そう。力そのものには、善いも悪いもない。たとえそれが、サイコパワーであっても、あるいは、殺意の波動であっても、な」
悪の力だと決めつけてしまっては、対処を見誤ることもある。そういいたいようだった。
だが、とダルシムは思う。
それだけではあるまい。
老仙人は、さらにその先のことまでも、見通しているのではないか。
すなわち、今ふたたび世に充満しつつある、あの男の気。シャドルー総帥、ベガのサイコパワー。その力の原泉を断ち切り、野望を潰えさせる、その方法を。
つまり、老仙人は、ベガを倒せるのではないか。
ダルシムが尋ねたそうにしているのがわかったのか、老仙人はふっと笑う。
「これが正義じゃ、正解じゃと表だっていうほどの脂っ気は、もうわしには残っておらんわ」
後は、おまえたちがやれ。
そう、いわれた気がした。
力の核心に迫ること。そして、繰り返し現れる、力を濫用する邪悪に対すること。
その意思。
それは、世代を超えて、伝えなければならない。
そう、いわれた。
知らず、修行僧の掌が、体の前で合わせられる。
闘いの構えではなかった。師に対して、そして大いなる力に対しての畏敬の形だった。
今や、昼の熱気が遠くなった夜に、虫の音色が戻ってきていた。
「クイーンズ リゾート(前)」

























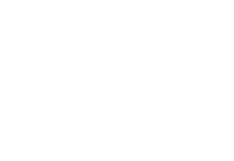 PlayStation および
PlayStation および