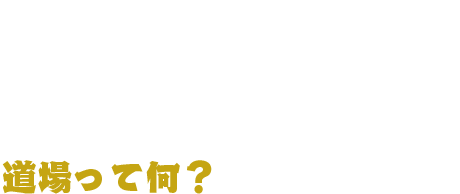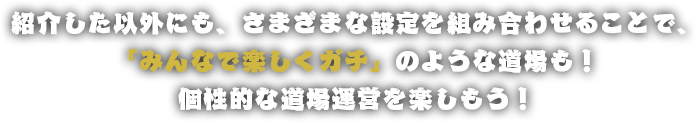南半球のブラジルでは、真夏のクリスマス。
誰もが陽気になるこの季節に、いつも明るいララが、なぜだか塞ぎ込んでいた......
ブルークリスマスインサマー
いつも陽気な人々がもっと陽気になって、誰もが笑顔で町を行き交う季節。ララ・マツダはその日七回目のため息をついた。
「......はあ」
二階にある自室から、ララはどことなく浮かれた人たちが歩きすぎる通りを見下ろす。透明な日差しに溢れた明るい部屋で、窓辺にほおづえを突いて、彼女はひとり沈んでいた。いつもの、太陽に負けないほどのまばゆい微笑みが姿を消し、整った横顔には物憂げな影が差している。
「......ふう」
豊かな濃色の髪をそっとかき上げて、ララは八回目の息をつく。そんな彼女を、部屋の外から伺う二組の目があった。
「......ずっとあんな調子なんだよ」
ファビオ・マツダが眼鏡の奥の目を細めて、ささやく。
「この季節は、毎年誰よりもはしゃいでいたあの子が......。何があったんだ?」
ユーイチロー・マツダは、ドアの隙間から心配げなまなざしを娘に向ける。ファビオが静かに首を振った。
「わかんないよ、父さんに心当たりは?」
うーんとユーイチローは小さくうなって腕組みする。
「覚えいてる限り、ララがこの時期に塞ぎ込んでいたのは......」
記憶を探って、言葉を継ぐ。
「あれだ、サンタさん撃退事件」
ああ、とファビオが肩をすくめる。
「あったなぁ。あれは父さん油断したね」
ユーイチローが苦々しげに顔をしかめる。サンタさん撃退事件は、ララが十歳ぐらいのときの話だった。サンタの扮装をしてプレゼントを持って行ったユーイチローが、寝ぼけたララに投げ飛ばされたのだ。
「ララのやつ、サンタさん捕まえてお礼を言うつもりだったんだよね、たしか」
「ああ......。完全に寝ていると思ったんだが」
幼いララは寝ぼけながらも、追撃の手を緩めなかった。
「しっかりクラッチされそうになったから、こっちは必死で逃げたよ」
「捕まったら父さんがサンタってバレちゃうもんね」
結局その騒動で、プレゼントを渡しそびれた。サンタを倒しちゃったと思い込んだララは、しばらくの間しょんぼりしていたものだった。
「うん......。でも父さん、さすがにそんな古いことで今さら落ち込まないと思うよ」
ううむ、とユーイチローは口元のひげを撫でる。ファビオはことさらに声を潜めた。
「父さん、やっぱり、これ......、男なんじゃないかな」
「男、か......」
ユーイチローは嘆息する。美しく成長したララにはもちろん、これまでにも浮いた話はあった。
「でも、ほら、父さんが怖いから続かないんだよ」
ファビオが咎めるように言うと、ユーイチローは慌てて首を振る。
「い、いや。中学の時のあれは私じゃないぞ。道場に呼んだのは確かだが、結局あの男を投げてぼこぼこ殴って追い出したのはララ本人だ」
ララにしてみれば、自分より弱い男はいやだった、ということらしい。
「それより、ファビオ、お前......。高校の時のあれ。あれはお前がやっただろう」
違う違うとファビオは抗議の声を上げる。
「あのとき、ララが上級生たちからしつこくナンパされてるって聞いて駆けつけたのはそうだけど......」
着いたときには倒れた男たちの間に、ララが汗一つかかずに立っていたのだという。
そんな武勇伝もいくつかあるが、ララは言い寄ってくる男たちを大概はあっさりとあしらっていた。彼女が物思いにふけるというのは、だから、よほどのことなのだ。
「むうう」
年頃の娘の父親として、ユーイチローは今一度深く嘆息した。
「あの子を悩ますとは......、一体どんな男だ」
当のララは、部屋の窓辺に寄せた椅子に、静かに腰を下ろしている。長いまつげを伏せ、しっとりした視線を、変わらず窓の外の通りに注いでいた。
陽が少し動いて、彼女のシャープな横顔に光を投げかける。時が止まりかけたような窓辺で、ララの形の良い唇が半ば開く。息を吸って、九回目のため息をつきかけたそのとき、通りをみつめていた切れ長の目がぱっと開いた。
「あっ」
小さく声をもらしたララの頬に、微笑みが戻る。
「来た!」
椅子を蹴って立ち上がると、ララはドアに突進した。つむじ風のように走り抜ける彼女を、ドアに貼りついていた兄と父親はとっさにかわす。
「来たって。父さん、見に行こう」
ファビオは、戸惑いに苦笑を浮かべた父親を促す。そして二人して、ララを追って玄関へと向かった。
玄関先で、ララは待ち人を出迎えていた。彼女と向き合う人影をうかがって、ユーイチローは思わずむうと唸る。
「あれが......、あの子の好み、なのか?」
ララが親しげに言葉を交わしている相手は、緑色の肌をした、毛むくじゃらの獣じみた男だった。知らず知らずのうちに眉をひそめて、ユーイチローは二人を見つめる。
ララが何か言ったのに応えて、獣男は牙をむき出しにして笑っていた。うおっうおっと吠えるような声がする。それから獣男は、爪の鋭い手で、大きなプレゼントの包みを差し出す。受け取ったララが歓声を上げた。夏の日差しがあふれる表通りに、ララの楽しげな笑い声が響いた。
「......ふ」
いつの間にか、ユーイチローの表情が緩んでいた。そう、相手がどんな男であれ、ララが幸せならばそれが一番だ。少しの寂しさを感じながら、娘の父親はそう考える。
大事そうにプレゼントの包みを抱えて今にも踊り出しそうなララの姿に、目を細める。そこには、正しいクリスマスの光景があった。
「あ! いいところにいた」
気がつくと、ララが玄関から駆け寄ってくるところだった。じゃーんと大きなプレゼントを両手で差し出してみせる。
「見てよ! 父ちゃんこれ、どう?」
包装紙を剥がれた箱には、同じぬいぐるみだけがたくさん詰まっていた。柔道着姿の老人らしき人形。そのひとつを、ユーイチローはつまみ上げる。

「これは......?」
ララがにっかりと笑う。
「そう。キンジローじいちゃん」
マツダ流柔術の開祖。ララたちにとっては祖父にあたるマツダ・キンジローその人をモデルにしたぬいぐるみだった。ララはえへんと得意げに胸を反らす。
「じいちゃんをモデルにした、マツダ流マスコット。マツダちゃんだよ」
なんだそりゃ、とファビオがいって、ララが説明する。箱を持って来たのはジミーという男で、彼が以前ブランカちゃんというマスコット人形を作っていたこと。ブランカちゃん人形は変なデザインだったけれど、日本でちょっと人気が出たらしいこと。ララはそれを真似して、マツダ流のマスコットを作ろうと思ったこと。
「発注が遅くなったから、クリスマスに間に合わないかと思って心配だったんだ」
ほっとしたような表情で、ララがいう。浮かない貌をしていたのは、それが原因だったらしい。
「では、その......。ジミー君とは......」
どうも思っていた展開とは違うと感じながら、ユーイチローはおずおずとそう切り出す。
「ジミー? うん。ジミーの知り合いの業者に、マスコット頼んだんだよ」
「それだけ?」
重ねて聞く父親に、ララはきょとんとした顔をする。
「うん、それだけ。マツダちゃんのデザインは自分でしたからね」
自慢げにそういうと、ララは人形をひとつつかんで高く掲げる。
「さあて、クリスマスにはこのマツダちゃん人形をばばーんと配って、マツダ流のアピールをするよ」
兄ちゃんも手伝ってね、と話を振られたファビオが苦笑する。いつの間にか、末っ子のショーンもやって来て、祖父に似た人形に笑い声を上げる。賑やかになる話し声に割り込むように、キッチンから妻のブレンダが食事の時間を告げる。
太陽の国の十二月。いつも陽気な人々がもっと陽気になるこの季節に、ユーイチロー・マツダはほっとしたように、この日何度目かの息をつく。いつもと変わらぬ、マツダ家のクリスマスが、そこにあった。

























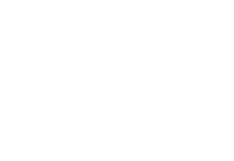 PlayStation および
PlayStation および